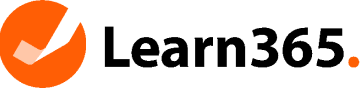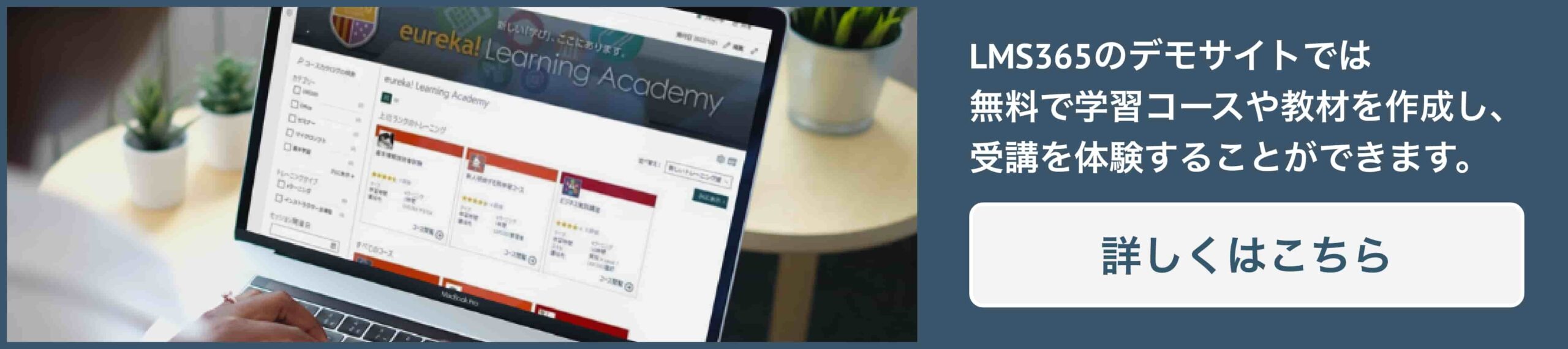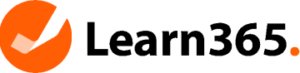eラーニングテストを活用することで、研修効果測定の効率化や受講者の理解度向上が期待できます。本記事では、eラーニングテストの種類、メリット、設計ノウハウ、導入事例などを詳しく解説します。
記事サマリー
企業の人事・研修担当者や教育機関の講師の皆さまは、受講者の習熟度を効率的に測定したいとお考えではないでしょうか。従来の紙試験や集合研修でのテストには時間と手間がかかりますが、eラーニングテストを活用すれば、場所を問わず効率的に受講者の理解度を確認できるのです。
平たく言うと、eラーニングテストとは、オンライン学習システム上で実施するデジタル試験のことです。これにより、テスト作成・採点の効率化と受講者の利便性向上を同時に実現できます。
具体的には、事前テストや事後テストなど多様な試験形式で学習効果を把握でき、テスト結果の分析を通じて研修内容の改善や個々のフォローにも役立てることが可能です。
本記事では、eラーニングテストの種類やメリット、効果的な設計のポイント、さらには実際の導入事例まで、体系的にご紹介していきます。
Microsoft365上で稼働する唯一のLMS「Learn365」は、WordやExcel・PowerPointなどの 慣れ親しんだツールで教材コンテンツを作成することができるため 、ストレスなく簡単に導入を進めることができます。 初期費用無料キャンペーンや30日間の無料デモサイト体験を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
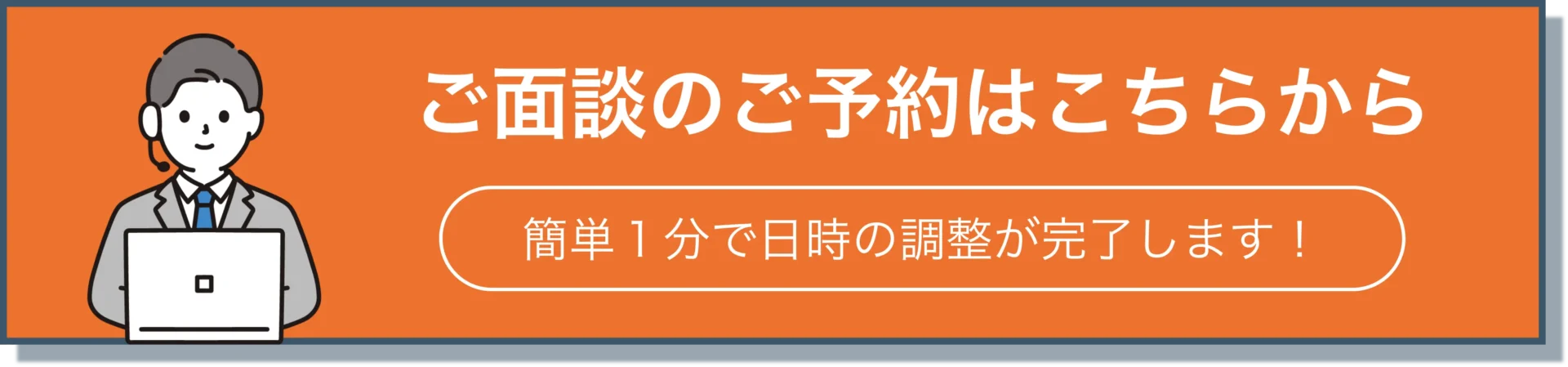
テストを実施する際の苦労とは?
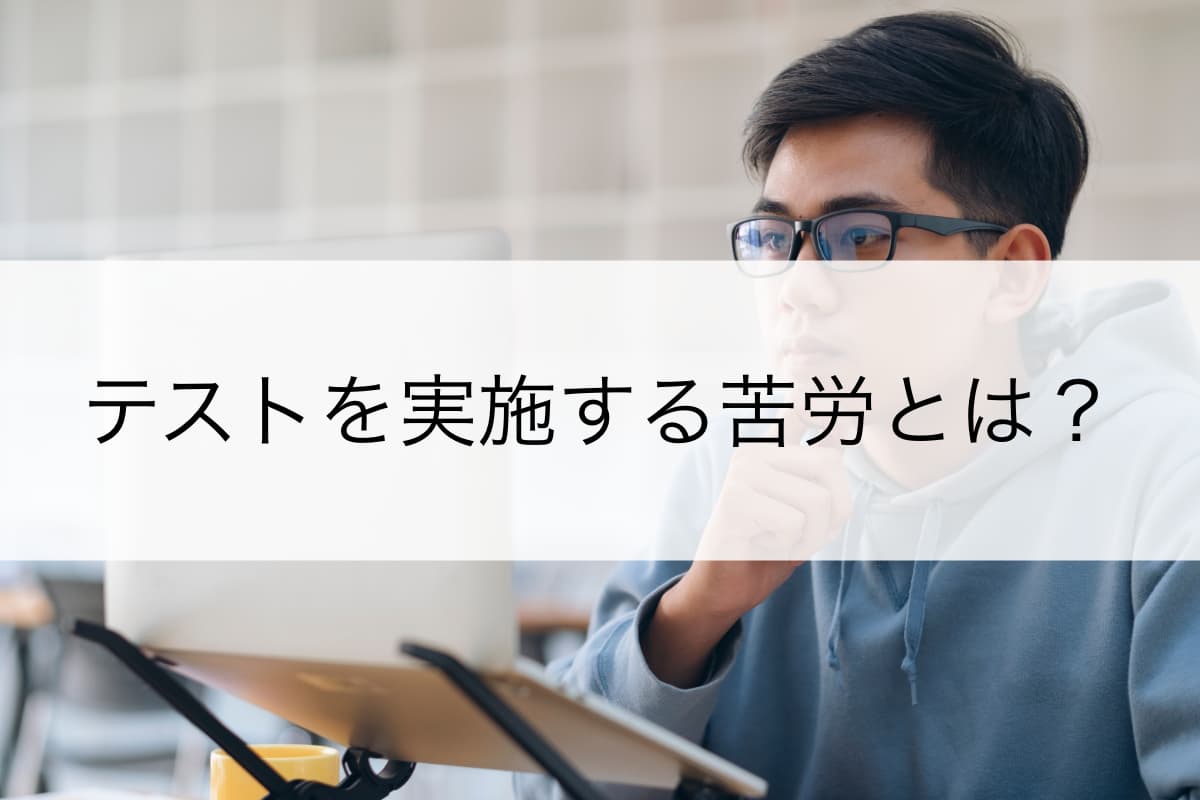
あなたの職場では、研修の一環でテストを実施する際にどのような課題を感じていませんか?
研修後のテスト実施には、実は多くの手間と時間がかかるものです。テストの目的は受講者の知識習得度合いを測ることですが、実際に問題を作成する段階では様々な検討事項が山積みになります。
例えば、「どのような内容を、どの形式で、何問出すか」「想定する解答や解説はどうするか」といった点を一つひとつ決めていく必要があります。全体の難易度を高くしすぎず簡単にもしすぎず、適切な問題を作成するのは、想像以上に労力のかかる作業と言えるでしょう。
さらに、実施後の採点・集計作業も担当者にとって大きな負担となります。解答者の人数が増えるほど採点に時間を要し、たとえば一人3分の採点でも50人分で合計約2時間30分もの時間がかかってしまいます。記述式の答案があれば部分点の基準を決める必要もあり、点数の集計まで含めると、一度のテストで膨大な作業量になってしまうのです。
このように従来のテスト運用には多大な苦労が伴うのではないでしょうか。
eラーニングシステムでテストの負担は軽減できる?
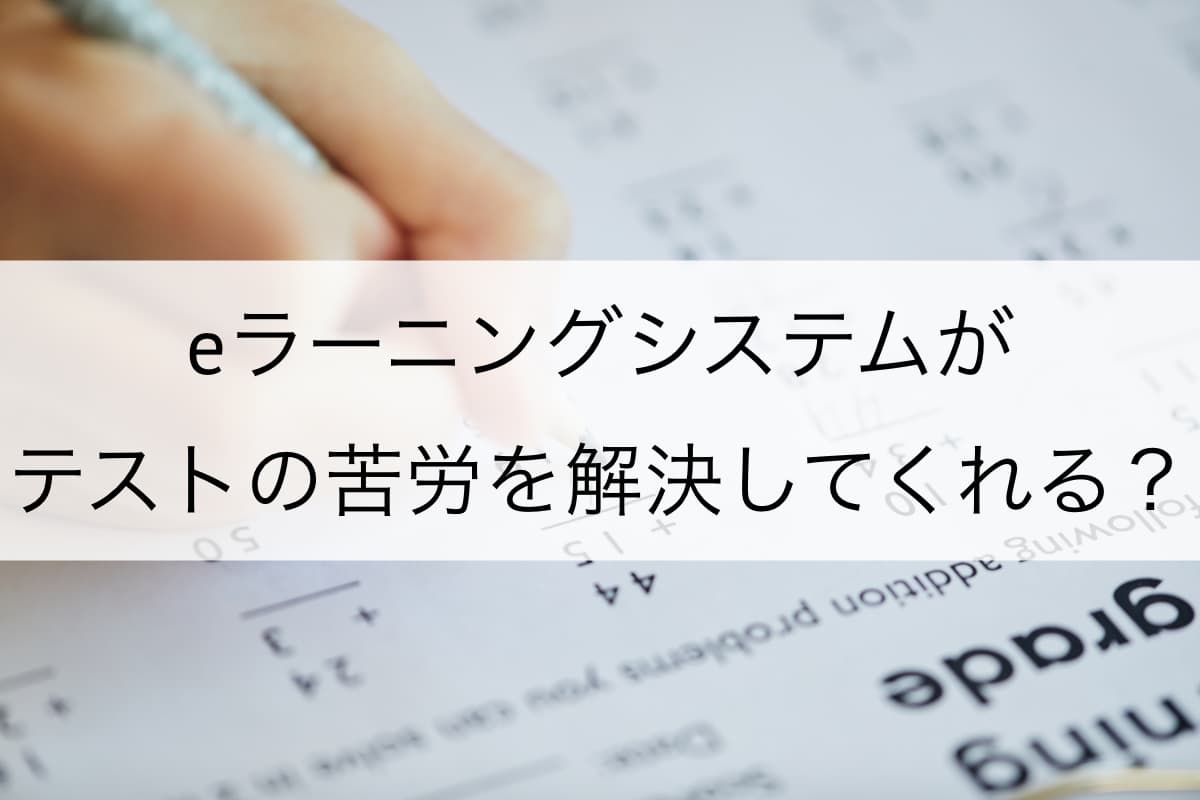
前章で述べたテスト作成・採点の負担も、eラーニングシステム(LMS)の導入で大幅に軽減できると考えられます。
まず、eラーニングとは何かを整理してみましょう。平たく言うと、eラーニングとはパソコンやスマートフォンなどを使い、インターネット上でいつでも学習できるオンライン学習形態のことです。時間や場所を選ばず受講できるメリットがある一方で、配布教材だけの学習では教材更新がしにくい等のデメリットもあります。
こうしたeラーニングを効果的に運用するためのシステムがeラーニングシステム(LMS)です。LMSは受講者管理や教材配信など学習管理に必要な機能を備えており、多くのLMSにはテスト機能も搭載されています。
このテスト機能を活用すれば、オンライン上で簡単にテストを作成・実施して解答を収集でき、採点・集計まで自動化できるのです。
eラーニングシステムのテスト機能とは?
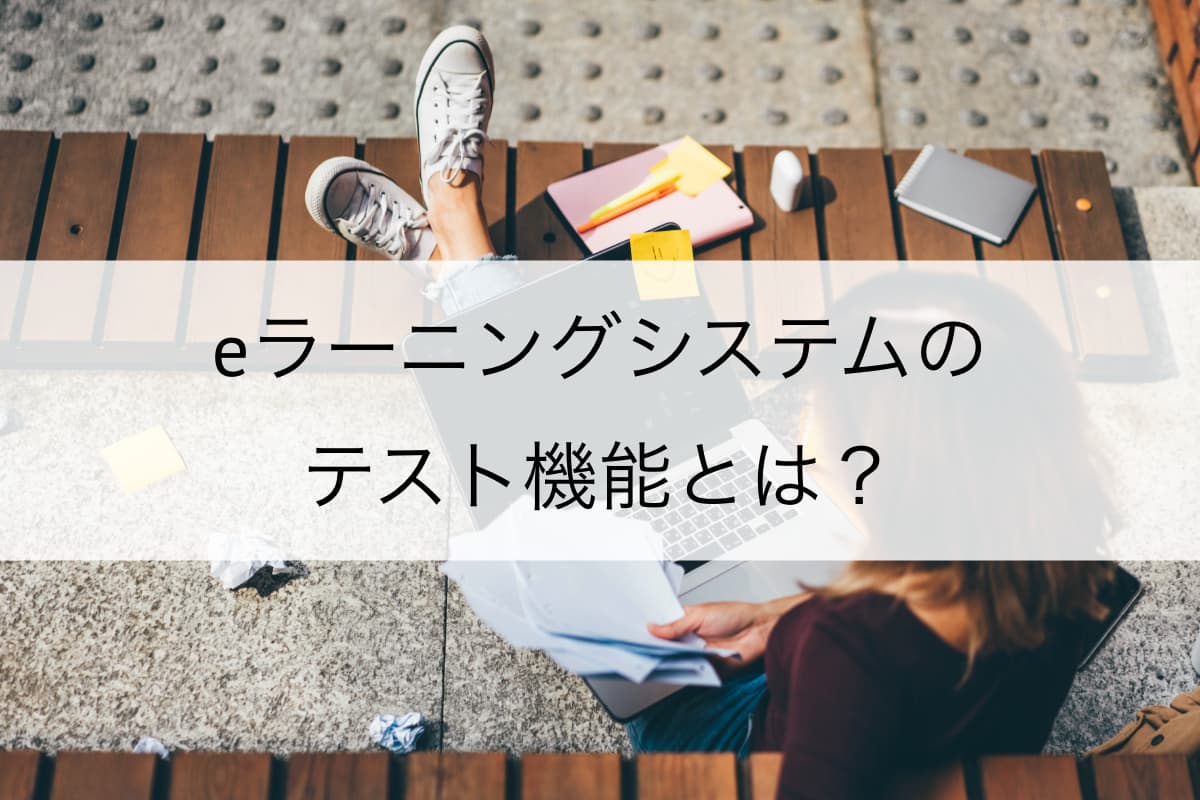
では、eラーニングシステムに搭載された主なテスト機能にはどのようなものがあるでしょうか。具体的にご紹介していきます。
テスト問題の作成機能
択一式(単一選択)、複数選択、○×形式、並べ替え、穴埋め、記述式など様々な出題形式の問題をオンライン上で作成可能です。普段WordやExcelで問題作成を行っている場合でも、対応するLMSであればこれらのファイルから問題を取り込んでテストを作成できるため、負担を減らすことができます。
また、問題ごとに制限時間を設けたり受験回数を制限したりといった細かな設定も行えるでしょう。
テストの詳細設定機能
合格点や受験可能期間の設定、受験できるユーザーグループの指定、結果表示の有無など細かな試験設定も行えます。システムによっては、用意した複数の設問からランダムに出題する機能もあり、毎回異なる問題セットで公正なテストを実施することも可能です。
テスト結果の集計・分析機能
テスト結果は自動で集計され、受講者全体の平均点や合格率を即座に把握できます。個人の点数はもちろん、グループ別の平均点比較など詳細な分析にも対応しており、以前のテスト結果との比較や各問題の正答率分析も容易に行えるでしょう。
これにより、従来講師にとって負担だった採点・集計作業を大幅に軽減でき、受講者の学習状況を的確に把握できるようになります。
eラーニングテストのメリット(受講者側)
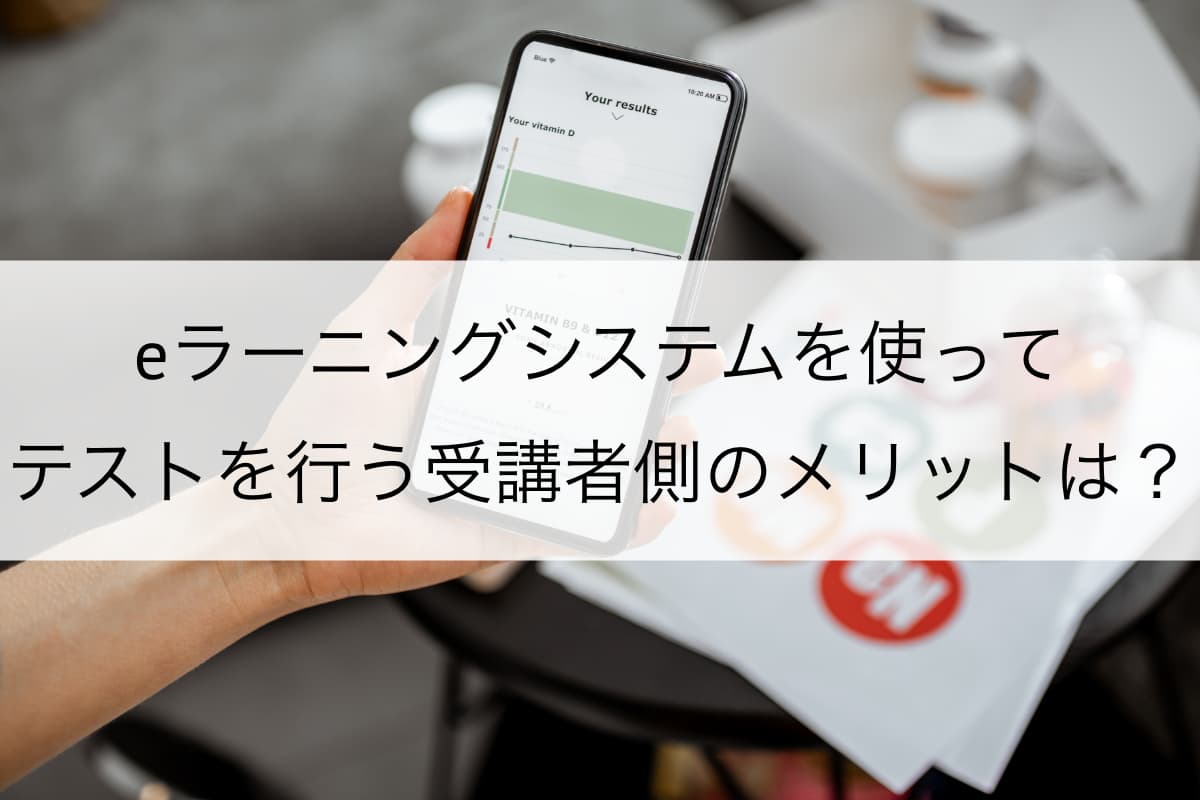
ここまで、eラーニングシステムの機能について解説してきました。では次に、実際にeラーニングテストを受ける受講者側にはどのようなメリットがあるでしょうか。
いつでもどこでも受験できる利便性
LMSを活用すれば、時間と場所に縛られずテストを受けることができます。最近のシステムはマルチデバイス対応のため、パソコンでもスマホでも24時間好きなタイミングで受験可能です。
例えば企業研修で全社員対象のテストを行う場合でも、各自が業務の合間に期限までに受けられるようになるため、一斉実施できない問題を解消し効率的に運用できるでしょう。
結果がすぐわかる即時性
選択式など自動採点できる設問であれば、テスト提出直後に自分の点数や合否が確認できます。テスト結果がすぐ分かることで、自分の理解度をその場で把握でき、どの分野を再学習すべきかといった弱点も早期に洗い出せるのです。
何度でも受けられる反復学習効果
LMSの設定によっては同じテストを複数回受験できるため、理解が不十分な場合の復習テストとしても活用できます。さらに、毎回のテストで問題を一部入れ替えるなどの機能を使えば、答えの丸暗記ではなく本質的な理解度チェックが可能になるでしょう。
eラーニングテストのメリット(管理者側)
一方で、企業の研修担当者や講師など管理者側にも多くのメリットがあると考えられます。
業務負担の大幅軽減
テストの自動採点・集計によって担当者の手作業が削減され、採点ミスも防げます。紙の問題配布や回答回収、成績表作成といった従来の業務がすべてオンラインで完結するため、研修担当者はより重要な業務に集中できるようになるでしょう。
受講状況の見える化
テスト結果など学習データの蓄積により、受講者ごとの理解度や習熟度を定量的に把握できます。テストの平均点推移や問題ごとの正答率を分析することで、研修内容の改善ポイントを発見したり、受講者への適切なフォローに役立てたりできるのです。
大規模研修への対応
eラーニングを使えば遠隔地や海外の受講者にも同一のテストを配信できるため、全国規模の研修でも一括してテストを実施・管理できます。試験会場の手配や日程調整が不要になり、研修計画を柔軟に組める点もメリットと言えるでしょう。
研修コストの削減
オンライン化によって紙の印刷や会場手配にかかる費用を削減できるのも利点です。地方拠点への出張費や人件費も減らせるため、トータルの研修コストを抑えつつ効率的に社員教育を実施できます。
eラーニングシステムを用いて効果の高いテストを作成するには?
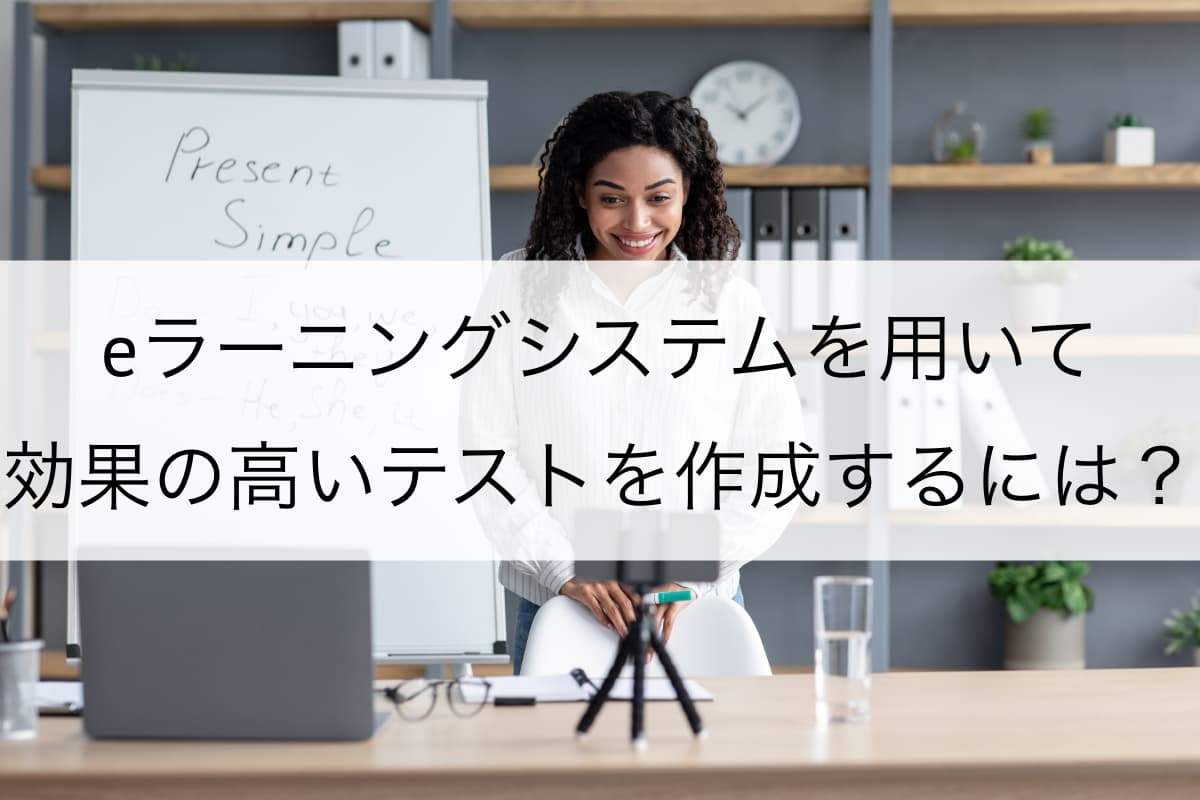
ここまで、eラーニングテストのメリットについて説明してきました。では、実際にeラーニングテストの効果を最大化するためには、どのような点に注意してテスト問題を設計・作成すればよいでしょうか。
1. 実施目的を明確にする
まずテストを実施する目的をはっきりさせておきましょう。テストで何を評価できるのか、受講者はテストを受けることで何を得られるのかを事前に共有しておくことが重要です。
目的が曖昧なままだと出題内容や求める解答の基準がぶれてしまい、テストの方向性を定められなくなってしまいます。
2. テストの種類や仕様を適切に選ぶ
目的に応じてテストの種類や出題形式を選定します。
具体的には、テストには以下のような種類があります。
- 受講前の実力を測る事前テスト
- 受講後の理解度を確認する事後テスト
- 単元ごとの理解度チェックである確認テスト
- コース全体の修了判定を行う修了テスト
また出題形式も択一式・複数選択式・○×式・記述式などから目的に合ったものを選びましょう。さらにテスト終了後に解説を表示するか、合格基準を何点に設定するかといった細かな仕様も事前に決めておくとよいでしょう。
ストレスを感じない問題作成
テストを受講者がストレスなく受けられるように工夫することも大切です。
例えば学習範囲外の内容を出題したり、設問文がわかりにくかったり、問題ごとの難易度のばらつきが大きすぎたりすると、受講者は不安に感じてしまうでしょう。問題文が文章ばかりで冗長な場合も意図が伝わりづらいため、必要に応じて図表や画像・動画を用いて直感的に理解できる設問にすることをおすすめします。
受講者の属性や理解度を考慮し、適切な難易度・表現で問題を作成することがポイントです。
4. テスト結果を分析して改善を続ける
テストを実施した後は、結果データやアンケートをもとに振り返りを行い、出題形式・難易度・合格基準に問題がなかったか確認します。
正答率が極端に低い問題や未回答が多かった問題は、問題文がわかりにくいか難しすぎる可能性があります。受講者からのフィードバックも参考にしながらテスト内容の改善を繰り返し、継続的にテストの質を向上させていきましょう。
テスト作成者・研修担当者の方は、ぜひ以上のポイントを参考にしてみてください。
eラーニングテストの導入事例
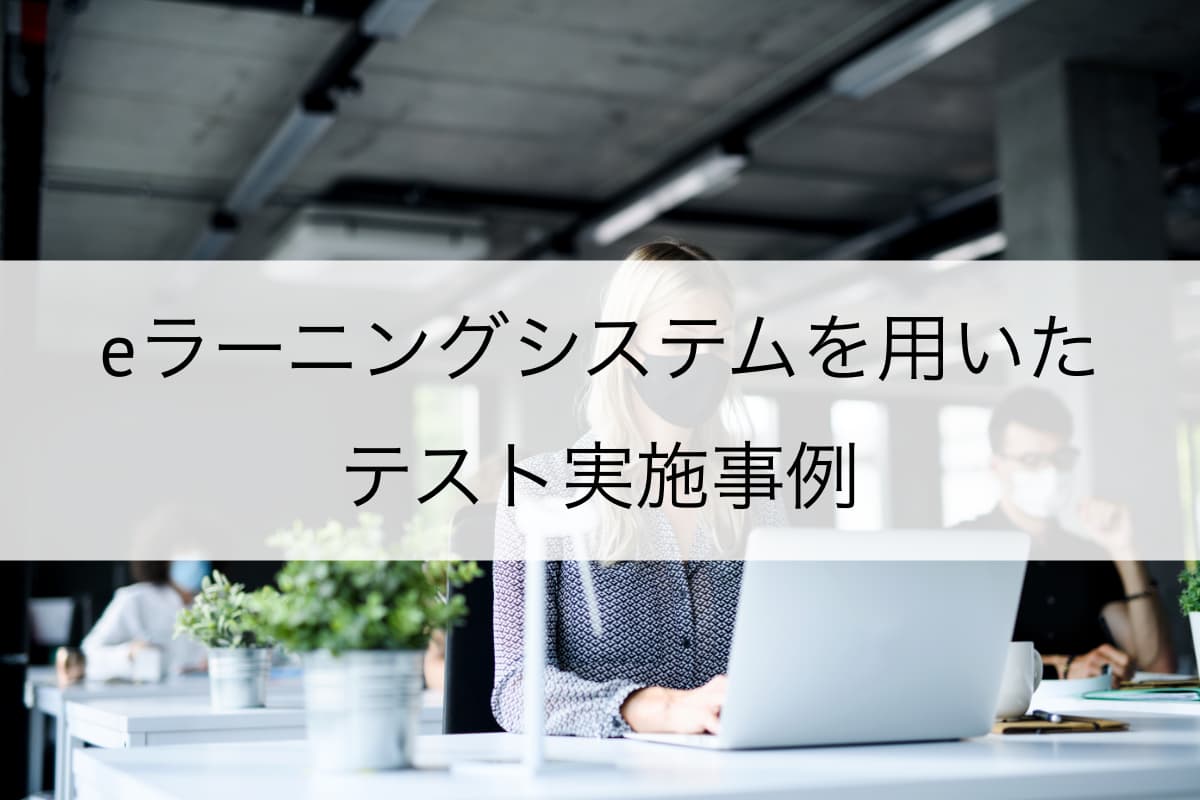
では次に、実際にeラーニングシステムのテスト機能を導入して課題を解決した事例をご紹介します。
- 福祉特化型人材サービスN社
- 私立大学J
- 飲食店チェーンM
- 個別指導教室I
- 金融教育機関S
自社に取り入れる場合もここで紹介する情報をぜひ役立ててください。
福祉特化型人材サービスN社の事例
事務職員の在宅勤務化により、紙のテスト結果をスキャン・郵送で集計する従来手法が困難になっていました。もともと成績表の郵送には1週間以上かかっていたため、受講者へのフィードバックが遅れる課題がありました。
そこでeラーニングシステムのテスト機能を導入した結果、受講者は回答直後に成績を確認でき、職員も在宅のままオンラインで成績管理が可能となったのです。
私立大学Jの事例
看護教育の場でeラーニングテストを活用し、学生の高度な知識習得状況を測定しています。定期的にオンラインテストを行って学習の定着度を把握し、レポート機能で得られたデータを分析して教育効果の検証を行いました。
大学ではeラーニング活用の有用性を定量的に測定し、結果を論文にまとめて看護学会で発表するなど教育改善に役立てています。
飲食店チェーンM社の事例
複雑な接客オペレーションを再現した独自のeラーニング教材を開発し、テスト機能で正しい動作や視線の向け方などをゲーム感覚で判定できるようにしました。
これによりOJT研修の内容が全店舗で均一化され、現場からも「研修負担が減った」「新人教育が楽になった」と好評です。今後は全国の店舗展開に合わせて導入を進め、調理研修やクレーム対応研修などにもeラーニングテストを活用していく予定です。
個別指導教室I社の事例
eラーニングシステムでテストを実施し、自動採点・自動成績表出力によって従来業務の負担を大きく軽減しました。また、教室ごと・エリアごと・法人全体でテスト結果データを共有できるため、生徒の学習状況を正確に把握・分析できるようになっています。
金融教育機関S社の事例
高度な金融知識講座をeラーニング化し、全国はもとより海外からも受講できるようにしました。PCだけでなくタブレットやスマホからも受講可能とし、受講者の利便性を向上しています。
さらにテスト機能で本試験と同じ形式の模擬試験を提供し、本番さながらの受験体験によって受講者の実力向上に貢献しています。
eラーニングテスト導入のポイント
ここまで様々な導入事例をご紹介してきました。では、自社でeラーニングテストを導入するにあたり、どのようなポイントを押さえておけばよいでしょうか。
導入目的と評価指標を明確に
eラーニングテストを導入する目的を社内で共有し、テスト結果をどう活用するかといった評価指標も定めておきましょう。目的が明確になれば、それに見合ったLMS選びやテスト設計がしやすくなり、導入後の効果検証も行いやすくなります。
自社に合ったLMSを選定
LMS(学習管理システム)の機能や使い勝手は製品によって様々です。テスト機能の有無・充実度はもちろん、操作性や費用、サポート体制も含めて、自社の研修規模やニーズに合ったシステムを選びましょう。
複数製品の無料トライアルやデモを実際に試し、現場で使いやすいかを確認してから導入するのがおすすめです。
小規模から試行し段階導入
いきなり全社導入するのではなく、まずは一部部署や特定の研修でパイロット導入してみましょう。小規模で試行することで課題や改善点が見つけやすくなります。
フィードバックを踏まえて運用を調整し、段階的に対象を拡大することで、現場の混乱を抑えスムーズに定着させることができるでしょう。
受講者への周知とサポート
オンラインテスト導入時には、受講者への事前案内とサポート体制の整備も欠かせません。操作マニュアルを配布したり事前にデモンストレーションを行ったりして、受講者が戸惑わず利用できるようにしましょう。
また問い合わせ窓口を用意し、ログイン方法が分からない等の質問に対応できるようにしておくと安心です。
まとめ
本記事では、eラーニングテストの概要から活用方法までを詳しく解説してきました。
まとめると、eラーニングテストとは、オンライン学習システム上で実施するデジタル試験のことで、従来の紙試験と比べて大幅な業務効率化と学習効果の向上を期待できるということです。
具体的なメリットとしては、受講者側では「いつでもどこでも受験できる」「結果がすぐわかる」「何度でも受けられる」といった利便性があり、管理者側では「業務負担の軽減」「受講状況の見える化」「大規模研修への対応」「コスト削減」などが挙げられます。
効果的なテスト設計のポイントは、「実施目的を明確にする」「適切なテスト種類・形式を選ぶ」「受講者がストレスを感じない問題作成」「結果分析による継続的改善」の4点です。
導入にあたっては、「目的と評価指標の明確化」「自社に合ったLMS選定」「段階的導入」「受講者サポート体制」を整えることが重要でしょう。
テスト実施は従来、講師や研修担当者にとって大きな負担でしたが、eラーニングシステムを活用すればその負担を削減しつつ効率的に研修を進めることができます。
紙のテスト運用に課題を感じている企業の方は、ぜひオンラインでのテスト実施を検討してみてはいかがでしょうか。
eラーニングシステムを導入するなら「Learn365(旧LMS365)」
eラーニングシステムを導入するなら「Learn365(旧LMS365)」がおすすめです。
導入するメリットは、以下の3つです。
- 導入が簡単
- 簡単にコンテンツを作成・配信・管理できる
- Microsoft365上で稼働する唯一のLMS
LMSの導入する企業にとって最も不安なのが、システムの構築と運用管理ではないでしょうか?
Learn365(旧LMS365)なら新たにサーバーを用意する必要はなく、既存システム(Microsoft365)にインストールをするだけなので簡単に導入できて、セキュリティ面も安心できます。
Word、Excelをはじめ、様々なファイル形式に対応しているため、従来から慣れ親しんだツールでコンテンツの作成や配信、管理ができます。そのため、導入後に操作がわかないという利用者や管理者のストレスは軽減されます。
Learn365(旧LMS365)なら導入前後のストレスを感じず、簡単に学習システムを構築できますので、この機会にぜひご利用ください。デモサイトでの体験もできますのでお気軽にお問い合わせください。
簡単に学習教材として利用できるLearn365(旧LMS365)がおすすめです。
まずはお気軽にお悩みや課題をご相談ください!
Learn365の導入実績
様々な業種・企業様にてLearn365をご利用いただいております。
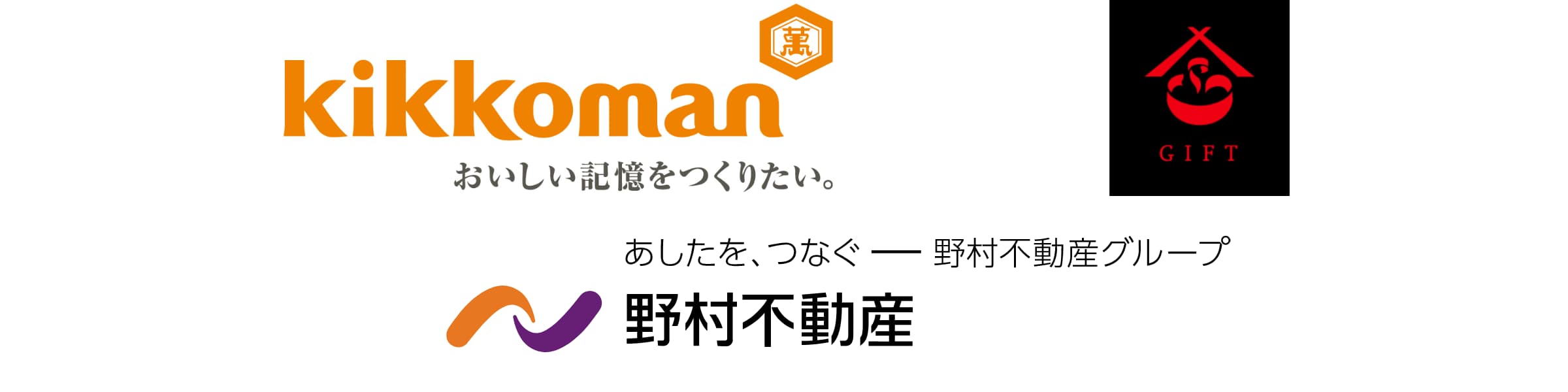
eラーニングを効果的に運用するなら、使い慣れたPowerPointやWordを
簡単に学習教材として利用できるLearn365がおすすめです。
まずはお気軽にお悩みや課題をご相談ください!