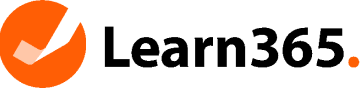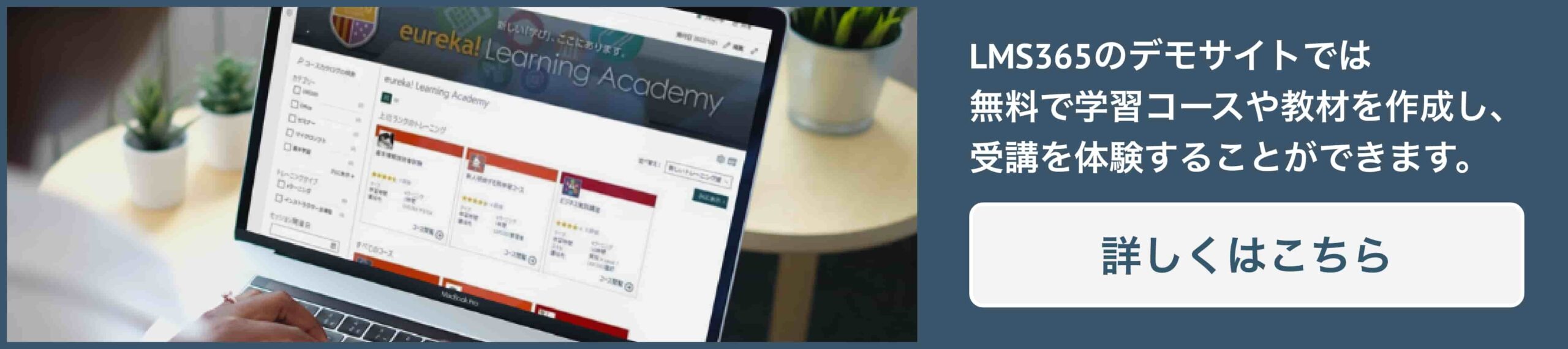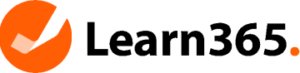eラーニングシステム費用の相場・内訳は?導入時の注意点も解説
サマリー
昨今のリモートワーク普及やDX推進の流れもあり、企業研修においてeラーニングの重要性はますます高まっていることをご存じでしょうか。
しかし、eラーニングシステムの導入を検討する際に多くの企業が直面するのが「費用の不透明さ」という問題です。機能にこだわりすぎて予算オーバーになったり、逆に予算内に収めようと必要な機能を諦めたりしては、自社にとって本当に必要なシステムが導入できたとは言えません。
そこでこの記事では、eラーニングシステム導入にかかる費用をクラウド型・オンプレミス型・スクラッチ開発の3タイプ別に比較し、それぞれの料金相場や特徴を詳しく解説いたします。また、eラーニング教材(コンテンツ)の調達方法ごとの費用や、社内制作と外注のメリット・デメリットについてもご紹介します。
さらに、eラーニングシステム導入で得られるメリットや、導入時に確認すべきポイントも解説し、企業の研修担当者がコストを抑えつつ最適なシステムを選ぶための情報を提供します。実際の企業事例を通じて、eラーニング導入による効果や成功のポイントもご紹介いたします。
本記事を読めば、eラーニング導入に必要なコストの全体像を把握し、自社に最適な方法を検討する参考になるでしょう。予算内に収めつつ、導入する目的を達成できる最適なeラーニングシステムを選ぶためにも、ぜひご活用ください。
Microsoft365上で稼働する唯一のLMS「Learn365」は、WordやExcel・PowerPointなどの 慣れ親しんだツールで教材コンテンツを作成することができるため 、ストレスなく簡単に導入を進めることができます。 初期費用無料キャンペーンや30日間の無料デモサイト体験を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
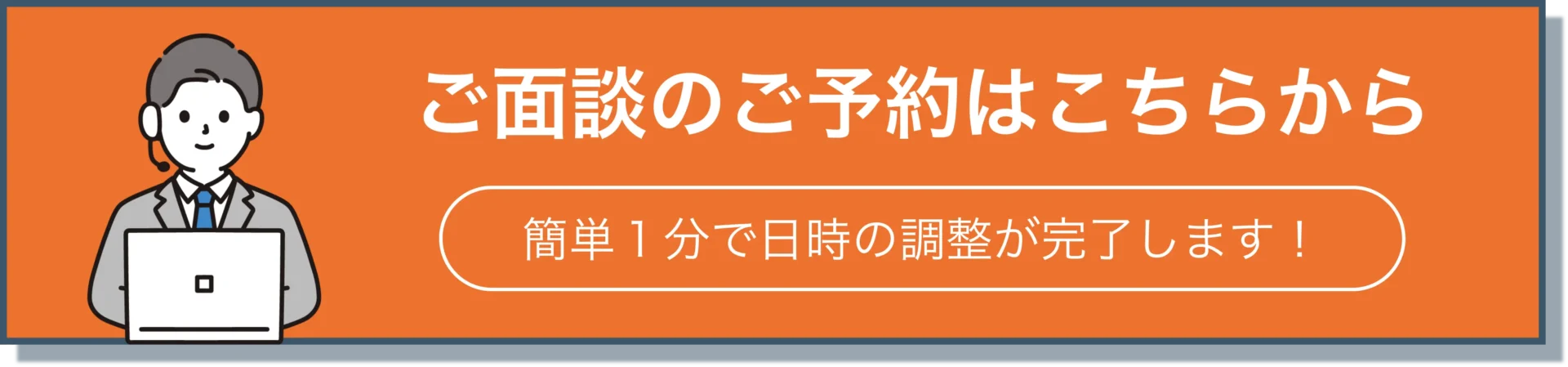
eラーニングシステムとはどのようなシステムなのでしょうか?
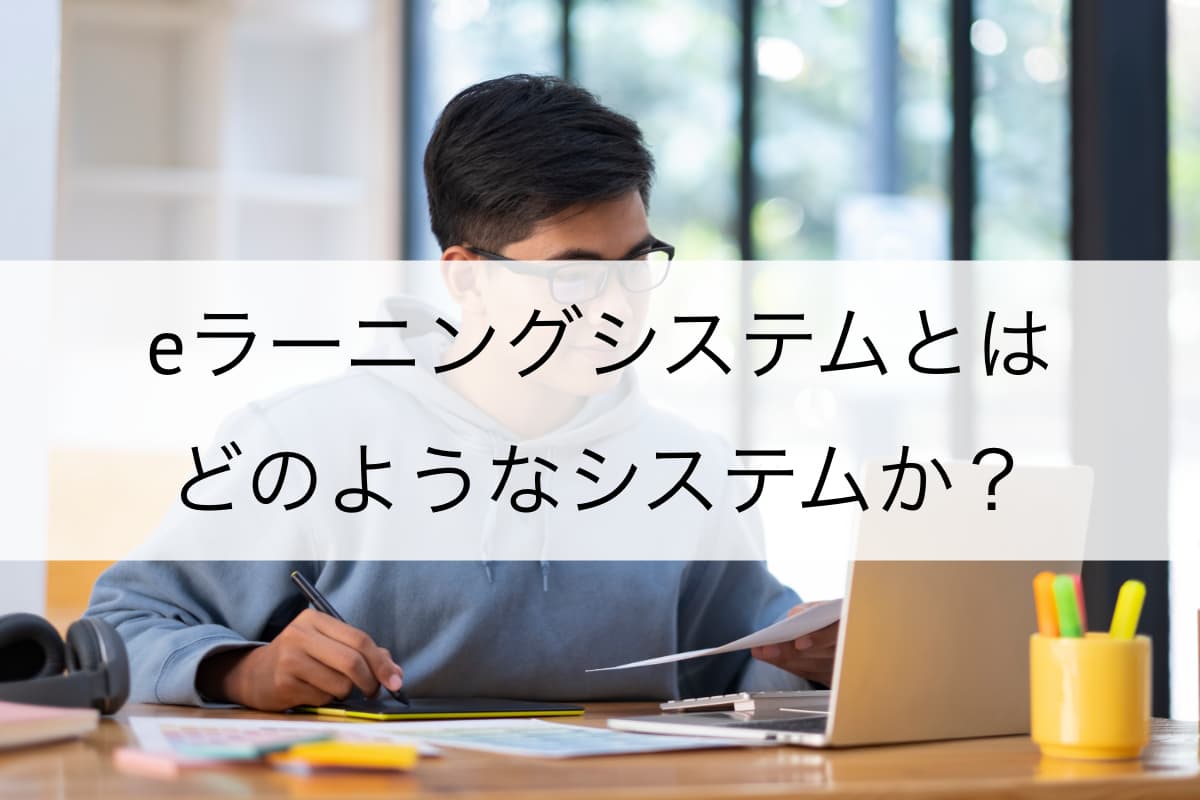
費用・料金相場を検討する前に、まずはeラーニングシステムの基礎知識をしっかりと理解しておく必要があります。平たく言うと、正確な知識なしには適切な費用対効果の判断ができないからです。
そこでこの章では、費用・料金相場を正しく評価できるように、以下3つの基礎知識について解説いたします。
- eラーニングシステムの基本機能
- eラーニングシステムのサービス
- eラーニングシステムの開発
では、順番に見ていきましょう。
eラーニングシステムの基本機能
eラーニングシステムの基本機能は、大きく分けて3つあります。詳細は以下の表をご参照ください。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| 受講者管理 |
|
| 教材管理 |
|
| 学習サポート |
|
eラーニングシステムは、端的に言えばeラーニングの効果を最大化させ、運用をスムーズに行うために必要不可欠なシステムです。
管理者の立場から見ると、受講者の進捗状況をデータとして一元管理できるため、個別にアドバイスをしたり、人事評価指標として活用したりもできます。これにより、受講者へ効果的な教育の実施が期待できるでしょう。また、適切な人事評価ができるため、組織全体の生産性を向上させる人材配置も可能になります。
一方で受講者側にとっても、コミュニティや掲示板で他の受講者や講師と繋がりを持てるため、モチベーションの維持・向上が期待できます。
このように、eラーニングシステムには教育効果を上げたり、運用をサポートしたりするための機能が備わっているのです。
なお、eラーニングシステムと同義の単語にLMS(Learning Management System)があります。LMSもeラーニングシステムと同様に、学習管理システムを指す際に用いられることが多いです。
eラーニングシステムのサービス
eラーニングシステムには自社サーバーに構築・開発する以外にも、クラウド型eラーニングシステムのようにライセンス料を支払ってサービスを利用する方法もあります。
クラウド型は、ライセンス料を払う代わりに、システムの構築や導入後のメンテナンスが不要となるため、企業の負担が軽減できるでしょう。また、気軽に他社サービスへの乗り換えもできるため、利便性にも優れています。
ライセンス料は月単位や年単位などサービス提供会社によって異なるため、どれくらいの期間で利用したいかで選ぶと良いでしょう。
eラーニングシステムの開発
eラーニングシステムの導入は、既存のクラウドサービスにアクセスする方法から自社サーバー上に1から開発する方法まで様々です。
自社サーバー上に開発する場合、テンプレートを活用するかどうかでも導入時の労力や費用が異なります。特に1からオリジナルのeラーニングシステムを開発する場合、システムエンジニアとプログラマーの人件費が加算されるため、通常で開発に数百万円以上がかかり、コンテンツ量や機能の追加によっては数千万規模となる場合もあります。
そのため、導入後に必要となる機能は事前に洗い出しておきましょう。
具体的には、教育コンテンツと学習管理など最低限の機能だけで良いという方はクラウドサービスが適しているでしょう。一方で、自社だけの独自性や他社との差別化を図りたいなら、オリジナルのeラーニングシステムを開発できるサービスを選ぶと良いでしょう。
【導入方法別】eラーニングシステムの費用・料金相場
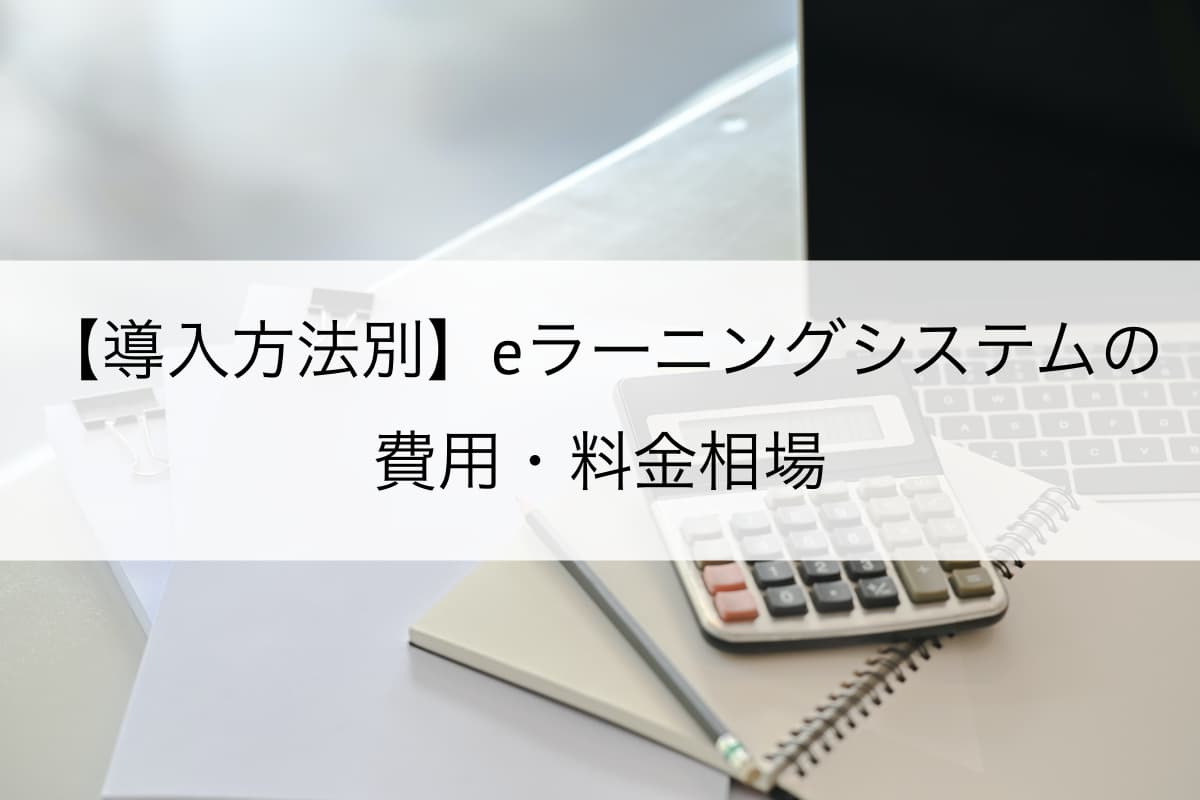
ここまで、eラーニングシステムの基本的な概念について解説してまいりました。では、実際の費用はどの程度かかるのでしょうか。
eラーニングシステムは、決して安い買い物ではありません。そのため、事前に導入費用の相場を知りたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこでこの章では、eラーニングシステムの3つの導入方法に分類して、費用・料金相場についてお伝えします。
- クラウド型
- オンプレミス型
- スクラッチ型
導入費用を考えるための参考にしていただければ幸いです。
クラウド型
クラウド型eラーニングシステムとは、提供会社のクラウドにアクセスしてサービスを利用するシステム形式です。
換言すれば、eラーニングシステムの構築や導入後のメンテナンスが不要になるため、利用者の負担が大幅に軽減される特徴があります。
料金相場は、以下の通りです。
| クラウド型 eラーニングシステム |
料金相場 |
|---|---|
| 初期費用 |
|
| 月額利用料 | (従量課金制)
(月額固定制)
|
※詳細は各社にお問い合わせください。
新たなシステムの構築が不要であるため、初期費用が抑えられます。初期費用は、50,000〜200,000円と開きがあるものの、自社サーバーへシステム構築をするオンプレミス型やスクラッチ型と比較すると、5〜10分の1以下の金額で済むでしょう。
オンプレミス型
オンプレミス型eラーニングシステムとは、自社サーバーに提供会社の用意したテンプレートを活用してeラーニングシステムを構築する方法です。
クラウドサービスのようにシステム構築されたサービスよりも導入費用や時間がかかるデメリットがあります。しかし、システム構築はテンプレートを利用できるため必要な機能を1から考える手間もありません。
既存機能の中から自社が運用していくために必要な機能だけを選べます。そのため、不要な機能を除外しシンプルな操作性を求めている方におすすめです。
ただし、自社サーバーがない場合はサーバーの構築から始めなければいけません。
料金相場は、以下の通りです。
| オンプレミス型 eラーニングシステム |
料金相場 |
|---|---|
| 初期費用 | (テンプレート・パッケージ費)
(初期導入費・初期研修費)
(サーバー本体費)
(周辺機器類)
(サーバー・ネットワークの構築費)
(カスタマイズ費)
|
| 運用費用 | (メンテナンス代)
|
※詳細は各社にお問い合わせください。
自社サーバーの構築費用等も含めると初期費用で100〜500万円前後で検討する必要があります。また、個別の機能についてカスタマイズを行う場合は個別見積となり100万円〜程度の予算が必要になるでしょう。
オンプレミス型は初期費用が高額ではありますが、ランニングコストを抑えることができる点や自社運用できる点がメリットとして挙げられます。
例えば、自社内で構築から運用管理まで完結できるため、情報漏洩や外部からのアクセス防止などセキュリティの強化ができます。自社制作のコンテンツ内に機密情報を取り扱うならオンプレミス型で導入しセキュリティの強化をすると良いでしょう。
なお、オンプレミス型の中にはオープンソースLMSを自社サーバーに導入する選択肢もあります。代表的なものに無償提供されている「Moodle(ムードル)」などがありますが、ソフトウェア自体は無料でもサーバー環境の構築や機能カスタマイズに手間・費用がかかる点には注意が必要です。
スクラッチ型
スクラッチ型eラーニングシステムとは、自社サーバーに完全オリジナルのeラーニングシステムを開発する導入方法のことです。
オンプレミス型のようなテンプレートはなく、自社運用していくために必要な機能から開発できる特徴があります。
料金相場は、以下の通りです。
| スクラッチ型 eラーニングシステム |
料金相場 |
|---|---|
| 初期費用 | (開発・構築から周辺環境費)
|
| 運用費用 | (メンテナンス代)
|
※詳細は各社にお問い合わせください。
開発には、個人のシステムエンジニアや小規模な企業に依頼した場合でも数百万円程度かかり、大手企業に依頼する場合だと数千万円単位の費用が必要になってきます。
スクラッチ型によるeラーニングシステムの導入はコスト面での負担は大きいものの、オリジナル機能だけで構築できるため導入後の運用がスムーズにできます。また大企業が導入する場合、受講者の意見を参考に幅広いニーズに応えた機能を追加でき柔軟性のあるシステム構築ができるメリットもあります。
eラーニング教材にかかる費用
ここまで、システム本体の費用について解説してまいりました。では、教材コンテンツの準備にはどの程度の費用がかかるのでしょうか。
eラーニングシステムの費用だけでなく、教材コンテンツを準備するための費用も考慮が必要です。ここでは、教材コンテンツの調達方法ごとの費用の目安をご紹介します。
市販コンテンツを利用する場合
学習内容に適した市販のeラーニング教材を利用する方法があります。LMS提供企業によっては、システム利用料に加えて定額料金で多数の標準コンテンツを受講できるプランも提供されています。
一般的な料金相場としては、受講者1人あたり月額数百円〜数千円程度でコンテンツ見放題となるサブスクリプション型や、教材1コースごとに月額数千〜数万円でレンタル利用する方式などがあります。
また、教材を買い切りで購入する場合は1コースあたり数十万〜数百万円といった初期費用が発生するケースもあります。
自社で教材を作成する場合
自社内にノウハウがあり講師を立てられる場合は、自社でeラーニング教材を制作することも可能です。
動画撮影用のカメラやマイク、編集ソフトなど必要な機材を揃える費用は数万円程度から用意でき、既存資料のスライド化やナレーション録音などを行えば、比較的低コストでコンテンツを内製できます。
ただし、撮影や編集にかかる手間・時間や、コンテンツ品質は社内の人材スキルに左右される点には注意が必要です。
教材制作を外注する場合
社内で教材を用意するのが難しい場合やプロ品質のコンテンツにしたい場合は、専門の制作会社に依頼する方法があります。
外注する場合の制作費用は、コンテンツの種類やボリュームによって大きく異なります。例えば、スライド資料をもとにナレーションを付けた動画コンテンツなら1本あたり約30万円、イラストや図解によるアニメーション動画では100万円前後、プロの俳優を起用したドラマ仕立ての動画では200万円以上かかることもあります。
費用は高くなりますが、受講者が興味を持ちやすい質の高い教材を制作できる点がメリットです。その一方で、自社の求める内容を反映させるために制作会社との打ち合わせや監修に時間を要するケースもあります。
<外注する場合のメリット>
- プロの制作会社に依頼することで、受講者が視聴しやすい質の高い教材を作成できる
- 業界に特化した内容や法律関連のコンテンツも、専門知識を持つスタッフや監修者を起用して対応できる場合がある
<外注する場合のデメリット>
- 制作費が高額になりやすく、予算負担が大きい
- 自社独自の事情を反映させるには制作会社との入念なすり合わせが必要で、完成までに時間がかかることもある
- 業種や専門分野に特化した内容では、制作会社に十分な知見がないと期待するクオリティの教材にならない恐れもある
<内製する場合のメリット>
- 自社の理念や業務内容など、独自の要素を教材にしっかり盛り込むことができる
- 外部に依頼するよりもコストを安価に抑えられる
- 社員が主体的に教材作成に関わることで、社内にノウハウが蓄積され、教育担当者自身のスキルアップにもつながる
<内製する場合のデメリット>
- コンテンツ制作の専門知識やノウハウが必要で、クオリティが外注に比べ見劣りする場合がある
- 社員が教材作成に割く手間や時間が発生する
- 教材開発に社内の人員リソースを割く必要があり、本来の業務に支障が出る可能性がある
おすすめeラーニングシステムの費用と特徴の比較

ここまで、eラーニングシステムの種類別費用と教材コンテンツの費用について解説してまいりました。では、実際の各社サービスはどのような特徴があるのでしょうか。
この章では実際に各社サービスを取り上げて、費用と製品の特徴について比較・検討します。導入検討中の方は、自社の予算や必要な機能の有無について考えるために、ご活用ください。
Learn365(旧LMS365)
Learn365(旧LMS365)の参考価格・サービスの特徴は、以下の通りです。
参考価格
- 初期費用:無料
- 利用価格:1,440,000円(1ライセンス年間4,800円)※スタンダードプランの場合
※最低利用300名〜
サービスの特徴
- Microsoft365と連動
- 効果的な学習の機会を作れる
- ハイブリットな教育コンテンツの作成
他社製品にはないLearn365(旧LMS365)最大の特徴は、Microsoft365と連動できるシステムであるということです。
Microsoftの代表的なツールは、資料作成やプレゼンテーションに用いられるPowerPointやWordです。社会人だけでなく学生にとっても馴染みのあるツールだけに、eラーニングシステムと連動できれば操作や導入後の管理もしやすいでしょう。
また、Microsoftの提供するコミュニケーションツールTeamsと連動しており、コンテンツ学習だけでなく講師や受講生同士のコミュニケーションも可能です。そのため、学習へのモチベーション維持や学習内容の深化にも効果が期待できます。
そのほか、動画コンテンツ・集合研修・ウェビナーなどスタイルの異なる研修を一括管理できるため、受講者の評価漏れを防ぎ適正な人事評価ができるという特徴もあります。
playse.ラーニング
playse.ラーニングの参考価格・サービスの特徴は、以下の通りです。
参考価格
- 初期費用:100,000円(無料トライアルあり)
- 利用価格:月額16,500円〜
※ご利用状況に合わせた従量課金制
サービスの特徴
- 約3,000レッスンの豊富な教材
- トレーニングマップにて学習フローを容易に把握
- オリジナル研修パックの作成
playse.ラーニングでは、約3,000のレッスンから学習目的にあったコンテンツを選び、学習できます。幅広いジャンルに対応しており、より深堀した学習ができるでしょう。
また独自のコンテンツをパッケージにした研修パックの作成もできるため、自社に特化した研修を行うこともできます。
なお、playse.ラーニングはシンプルなUIと手厚いサポートでも定評があり、初めてLMSを導入する企業にも使いやすいサービスです。
Teachme Biz
Teachme Bizの参考価格・サービスの特徴は、以下の通りです。
参考価格
- 初期費用:要問い合わせ
- 利用価格:50,000〜300,000円
サービスの特徴
- テンプレートで教材を簡単に作成
- 作業指示の徹底と簡略化
- 受講者の属性に合わせたコースの作成
オリジナルの教材の制作がスムーズにできれば、コンテンツの充実にも力が入れられます。そこでおすすめなのが、Teachme Bizの教材作成機能です。様々なテンプレート準備されているので、初心者でも簡単かつスムーズにコンテンツの作成ができます。Teachme Bizは元々業務マニュアル作成ツールとして広く普及した経緯があり、現場のノウハウを動画教材として蓄積する用途にも適しています。
Cloud Campus
Cloud Campusの参考価格・サービスの特徴は、以下の通りです。
参考価格
- 初期費用:100,000〜500,000円
- 利用価格:70,000〜360,000円(月額固定制)
サービスの特徴
- 顔認証システム
- パスワードポリシーの設定
Cloud Campusは、すべての授業をeラーニングで行う文部科学省認可のサイバー大学が開発したクラウド型eラーニングプラットフォームです。
サービス最大の特徴は強固なセキュリティにあります。顔認証システムを開発なしで導入できたり企業ごとにパスワードポリシーをカスタマイズできたりします。
そのため、多くの企業が出入りするクラウド型のプラットフォームでも外部からの不正アクセスや情報漏洩を防止できるセキュリティの構築が可能です。特に自社制作のコンテンツ内に機密情報が含まれている企業ならセキュリティ強化で安心して利用できるでしょう。
サイバー大学で培われたノウハウを活かし、大手企業から教育機関まで幅広く利用されています。
AirCourse
AirCourseの参考価格・サービスの特徴は、以下の通りです。
参考価格
- 初期費用:無料
- 利用価格:ユーザー1人あたり0〜600円/月額
サービスの特徴
- オリジナルコンテンツを簡単にアップロード
- 受講者の学習管理レポート機能
AirCourseは、ユーザー数に応じた従量課金制です。「フリー」「ベーシック」「コンテンツプラス」とコースに応じて料金が設定されており比較的安価でサービスを利用できます。
また初期費用が無料であるため導入費用を抑えたい方に向いています。ビジネススキルからITスキルまで1,500本以上の研修動画コンテンツがあらかじめ用意されているため、導入後すぐに社員教育を開始できる点も魅力です。
eラーニングシステムを導入するメリット
ここまで、様々なeラーニングシステムの特徴や費用について解説してまいりました。では、eラーニングシステムを導入することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。
eラーニングシステムの導入には費用がかかりますが、得られるメリットは多数あります。管理者側・受講者側それぞれに利点がありますが、ここでは管理者側が得られるeラーニングシステム導入のメリットを見ていきましょう。
管理者側が得られる主なメリットは次の3つです。
- 費用・労力を削減できる
- 受講者ごとの学習管理が簡単
- セキュリティの安全性が高まる
メリットを知っておくことで、eラーニングシステムを導入すべきかどうかを検討しやすくなるため、ここで押さえておきましょう。
費用・労力を削減できる
eラーニングシステムを導入すると、オフラインで学習を行う場合に比べ費用や労力の削減ができます。
オフライン学習では、場所の確保・講師の手配・教材の準備・参加者管理など多くの費用や労力がかかることも少なくありません。全国各地で学習を行いたい場合、場所や講師の準備にも手間がかかります。また参加者が多い場合は教材の準備にも費用や手間がかかり、参加者を管理するリソースも必要となります。
例えば、株式会社産労総合研究所の調査データによれば、集合研修を実施する場合には従業員1人あたり年間で約3万円の研修費用がかかるという結果が報告されています。一方、eラーニングなら1人あたり数千円程度で受講できるケースもあり、従来型研修と比べ大幅なコスト削減が期待できます。
しかし、eラーニングシステムを導入すればこれらを全て解決できます。オンラインで学習が可能なため全国どこにいても受講でき、場所や講師をそれぞれ確保する必要もありません。
eラーニングシステムを導入する際は費用がかかりますが、トータルで見ると研修にかかる費用や労力を削減できるため自社に合ったシステムの導入は価値のあるものとなるでしょう。
受講者ごとの学習管理が簡単
eラーニングシステムは、受講者ごとの学習管理が簡単にできることもメリットとして挙げられます。
参加者が多いと名簿の作成や出欠確認に手間がかかりますが、eラーニングシステムであればシステム上でリストを確認するだけで良いので、手間や時間をかけずに出欠確認が可能です。
また出欠確認だけでなく受講者ごとの学習進捗もチェックできるため、最後まで学習していない人の把握も可能で受講者ごとの学習量の差を軽減できます。
セキュリティの安全性が高まる
強固なセキュリティを特長としているeラーニングシステムであれば現状よりもセキュリティ強化が期待でき、より安全性が高まります。
機密情報を扱っている・不正アクセスや情報漏洩が心配という場合は、eラーニングシステムを導入してセキュリティ強化に努めるのも良いでしょう。
ここで押さえておきたいのは、eラーニングと従来型の集合研修を組み合わせた”ハイブリッド研修”を取り入れる動きも広がっていることです。それぞれの長所を活かすことで研修効果を一層高めることができます。
導入企業の成功事例
ここまで、eラーニングシステム導入のメリットについて解説してまいりました。では、実際に導入した企業ではどのような効果が得られているのでしょうか。
具体的な企業事例をご紹介します。
B社(製造業)
社内講師制度の導入とeラーニング化により、研修コストを約60%削減しました。従来、年間400万円かかっていた外部研修費を大幅に圧縮し、社員の離職率も研修導入前より8%改善しています。
C(サービス業)
営業研修を対面からeラーニングに切り替えた結果、受講者のテスト合格率が向上し、研修後3か月の売上が前年比で110%となりました。全国の店舗スタッフが同じ水準の研修を受けられるようになり、教育格差の解消にもつながっています。
D社(IT業)
社員の技術研修にeラーニングを導入した結果、研修にかかる移動や出張費を年間500万円以上削減できました。全国の技術者がいつでも最新教材で学べるようになり、スキル習得のスピードも向上しています。
E社(小売業)
店舗スタッフ向けコンプライアンス研修をeラーニング化したことで、受講率が全店で100%に達しました。以前は店舗都合で受講漏れがありましたが、オンライン化により従業員が空き時間に自主的に学習できるようになり、研修定着率が向上しています。
eラーニングシステム選定時のチェックポイント
ここまで、eラーニングシステムの導入事例について見てまいりました。では、自社に最適なシステムを選ぶためには、どのようなポイントに注意すれば良いのでしょうか。
eラーニングシステムを選定する際には費用以外にも以下のポイントを確認すると自社に合った製品を見極めやすくなります。
ポイント① 既存コンテンツの充実度
自社のニーズに合った学習コンテンツがあらかじめ用意されているか、あるいは自社で作成した教材をアップロードできるかを確認しましょう。
ポイント② 操作性
受講者・管理者ともに使いやすいUIであるかが重要です。画面が複雑すぎると学習意欲の低下や管理の手間増加につながるため、実際に試用して直感的に操作できるか確かめましょう。
ポイント③ 学習管理のしやすさ
受講者の進捗や成績を管理・把握する機能が整っているか確認しましょう。受講状況の一覧表示や絞り込み、レポートの自動集計など担当者の管理負担を軽減する機能があると便利です。
ポイント④ 分析・評価機能
テスト結果の分析や学習効果の可視化など、データに基づき評価できる仕組みが備わっているかチェックします。また、SCORMやxAPIといったeラーニング標準規格への対応状況も確認しておくと良いでしょう。研修効果を測定できれば、導入後の研修内容の改善にも役立ちます。
ポイント⑤ マルチデバイス対応
パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットなど様々なデバイスで受講できるかも重要です。受講者が好きなタイミングで学べるよう、通勤中のスマホ利用などにも対応したシステムを選びましょう。
ポイント⑥ サポート体制
導入後の操作方法の問い合わせやトラブルに対して提供ベンダーがどの程度サポートしてくれるかも確認ポイントです。マニュアルの有無、問い合わせ対応の迅速さやサポート窓口の充実度などを比較しておきましょう。
なお、多くのサービスでは無料トライアルやデモ環境が提供されています。導入前に実際の操作感や機能を確認し、自社に合ったシステムか見極めましょう。
eラーニング導入のステップ
ここまで、eラーニングシステムの選定ポイントについて解説してまいりました。では、実際に導入を進める際は、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。
eラーニング導入の一般的なステップをご紹介します。
1. 目的・対象の明確化
eラーニング導入の目的や学習対象者を明確に設定します。研修のねらいや受講者のニーズを整理することで、費用対効果を最大化できます。
2. システムの選定
自社の要件に合ったLMSを比較検討します。他社の導入事例やユーザーレビューも参考に、自社に適したサービスかを見極めましょう。多くのサービスで無料トライアルが可能なため、実際に操作性や機能を試しながら選びましょう。
3. 提供会社との契約
導入するシステムが決まったら提供企業との契約手続きを行います。料金プランやサポート内容を確認し、導入後の運用計画をすり合わせておきます。
4. 環境の構築
ベンダーと協力して自社向けにLMSの利用環境を整備します。システムへのユーザー登録や権限設定、必要に応じた機能のカスタマイズなどを実施します。
5. 運用準備
本番運用に向けて受講者情報の登録や教材コンテンツのアップロードを行います。試験的に動作確認を行い、不備がないか最終チェックをしましょう。
6. 運用開始
準備が整ったらいよいよ研修をスタートします。初期段階は受講者からの問い合わせ対応などフォロー体制も準備し、円滑な運用を心がけます。運用開始後も定期的に利用状況を分析し、研修内容の改善に役立てましょう。
よくある質問
ここまで、eラーニング導入の手順について解説してまいりました。では、実際に導入を検討される企業から寄せられる疑問にはどのようなものがあるのでしょうか。
よくいただくご質問とその回答をご紹介します。
Q1. eラーニングシステム導入にはどれくらい費用がかかりますか?
A. 企業の規模や導入するシステムの種類によって異なります。クラウド型LMSであれば初期費用無料〜数十万円、月額費用も数万円程度から利用可能です。オンプレミス型の場合はサーバー構築費用などがかかり、初期費用で数百万円規模になるケースもありますが、長期的な運用ではクラウド型より割安になることもあります。
なお、Microsoft365と統合可能なLMS(例:Learn365)を選べば、既存の社内環境を活用でき導入の負担を軽減できます。
Q2. eラーニング導入コストを抑えるポイントはありますか?
A. まずは無料トライアルや低価格プランを提供しているLMSを検討しましょう。自社で教材コンテンツを内製できる場合は、外注費を削減してコストを大幅に抑えられます。さらに、国や自治体の助成金制度を活用できれば導入費用の一部を補助してもらうことも可能です。
Q3. eラーニングシステム導入にあたり社内で準備すべきことは何ですか?
A. 受講に必要なPC・タブレットやネットワーク環境の整備が第一です。また、LMSを運用する担当者や管理者を決め、社内向けの使い方マニュアルを用意しておくとスムーズに定着します。試験導入期間を設けて一部の社員からフィードバックを集め、課題を洗い出してから本格導入すると失敗が少ないでしょう。
Q4. eラーニング導入の効果はどれくらいで実感できますか?
A. 新人研修や商品知識研修などでは、早ければ数週間~数か月で受講者の理解度向上や業務効率化などの効果が現れます。一方で、人材育成全体の成果(定着率や業績向上など)を測るには半年から1年程度の継続運用が必要でしょう。
重要なのは、導入後も定期的に効果測定を行いコンテンツや運用方法を改善し続けることです。
Q5. eラーニング導入にあたり社内の理解を得るにはどうすれば良いですか?
A. 経営層や現場の管理職に対して、eラーニング導入による具体的なメリットを示すことが重要です。例えば、「研修費用を◯割削減できる」「従業員のスキマ時間を活用して生産性向上が見込める」といったデータや他社の成功事例を共有しましょう。
さらに、実際にお試しでLMSを利用してもらい、その利便性を体感してもらうことで社内の理解と協力を得やすくなります。
まとめ:eラーニングシステムにかかる費用を把握しておこう
以上、eラーニングシステムにかかる費用・料金相場について詳しく解説してまいりました。
結論から言えば、eラーニングシステムの導入を検討するなら事前に費用を把握し、予算に合ったサービスを選べるようになっておくことが重要です。要点をまとめると以下の通りです。
- 3つの導入方法により料金の相場が異なる
- 料金と一緒に必要な機能があるかを確認しておく
- 導入費には「初期費用」「運用費用」がある
- 教材コンテンツの調達にも費用がかかるので、準備方法を事前に検討しておく
端的に言えば、eラーニングシステムと一口に言っても導入方法や料金制度によって費用は全く異なります。特にクラウド型eラーニングシステムならシステムの構築からメンテナンスまでが不要であり、費用に加え導入後の企業の負担も軽減できるでしょう。
また導入後の運用費についても考えておく必要があります。特にオンプレミス型・スクラッチ型eラーニングシステムはサーバーやメンテナンス費用など継続的に費用が発生するため注意が必要です。
なお、厚生労働省の人材開発支援助成金などeラーニング導入に活用できる助成金・補助金制度も存在します。条件を満たせば費用の一部を公的補助で賄える可能性があるため該当する場合は活用を検討しましょう。
代表的な制度として、厚生労働省の「人材開発支援助成金」、中小企業庁の「IT導入補助金」、東京都の「オンラインスキルアップ助成金」などがあります。
これらを踏まえ、予算内で自社に最適なeラーニングシステムの導入ができるようにこの記事をご活用いただければ幸いです。
eラーニング導入は初期費用こそかかりますが、長期的には研修運営の効率化や社員の生産性向上につながり、十分に投資価値のある施策と言えるでしょう。政府によるデジタル人材育成の推進もあり、企業のeラーニング活用は今後ますます重要になると思われます。
eラーニングシステムを導入するなら「Learn365(旧LMS365)」
最後に、eラーニングシステムを導入するなら「Learn365(旧LMS365)」をおすすめいたします。導入するメリットは以下の3つです。
- 導入が簡単
- 簡単にコンテンツを作成・配信・管理できる
- Microsoft365上で動作する唯一のLMS
LMSを導入する企業にとって最も不安なのがシステムの構築と運用管理ではないでしょうか?Learn365(旧LMS365)なら新たにサーバーを用意する必要はなく既存システム(Microsoft365)と統合するだけなので簡単に導入できてセキュリティ面も安心できます。
またLearn365(旧LMS365)はMicrosoftに組み込める唯一のシステムです。Word、Excelをはじめ様々なファイル形式に対応しているため、従来から慣れ親しんだツールでコンテンツの作成や配信・管理ができます。そのため導入後に操作がわからないという利用者や管理者のストレスは軽減されます。
Learn365(旧LMS365)なら導入前後のストレスを感じず簡単に学習システムを構築できますので、この機会にぜひご利用ください。デモサイトでの体験もできますのでお気軽にお問い合わせください。
eラーニングを効果的に運用するなら、使い慣れたPowerPointやWordを簡単に学習教材として利用できるLearn365(旧LMS365)がおすすめです。まずはお気軽にお悩みや課題をご相談ください!
簡単に学習教材として利用できるLearn365(旧LMS365)がおすすめです。
まずはお気軽にお悩みや課題をご相談ください!
Learn365の導入実績
様々な業種・企業様にてLearn365をご利用いただいております。
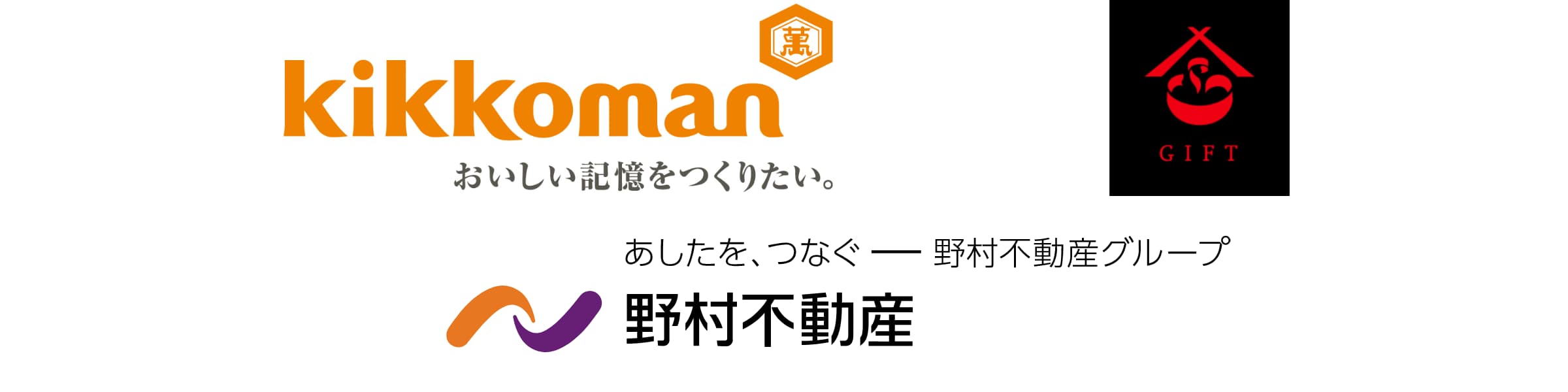
eラーニングを効果的に運用するなら、使い慣れたPowerPointやWordを
簡単に学習教材として利用できるLearn365がおすすめです。
まずはお気軽にお悩みや課題をご相談ください!